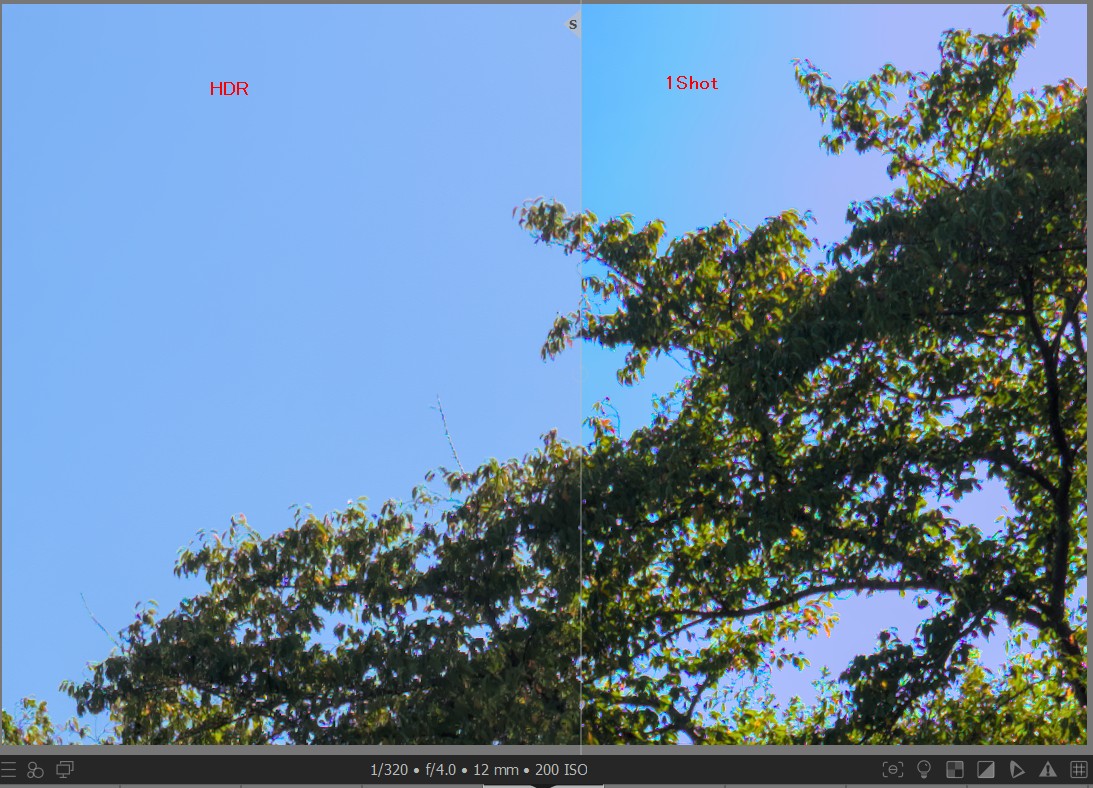1)概観
前回述べましたように、RAWのHDR画像を得るためには、HDR撮影モードが使えず、ブラケット撮影した数枚のRAWファイルをdakrtableで合成する方法が基本です。
これは、HDRモードで撮影した場合には、出力がJpegに限定されるためです。
しかし、例外があります。この例外に関する情報は少ないので、見落としがある可能性があります。
1-1)オリンパスのカメラ
E-PL7(2014年 9月20日 発売)以降のオリンパスのカメラでは、HDRモードで、RAW画像を保存することもできます。画像保存をJpegにしていれば、RAWは保存されません。画像保尊モードをRAWにしていると、JpegとRAWファイルが保存されます。
このRAWファイルの拡張子はORFで、通常のRAWファイルと同じです。ファイルサイズも代わり映えしないので、12EVのデータしか保持していないと思われます。
とはいえ、Jpegよりは、圧倒的に多い情報量です。
オリンパスのHDR撮影のRAWファイルは、HDRのJpegを作る時に使ったRAWファイルを保存したものと考えられます。つまり、Jpegに変換する時に、ダイナミックレンジを8EV近くに圧縮しているのでHDRの広いダイナミックレンジの情報をもってはいません。
1-2)富士フイルムのX-T4
Chris LeeさんによるとX-T4を含むHDR撮影に対応したいくつかの富士フイルム カメラでは、RAWファイルを作ることができます。
ただし、富士フイルムのHDR撮影には、カメラによって、RAW保存ができる機種とできない機種があります。
RAW ファイルには実際には1 つの .RAF ファイル内に3 つの別々の写真が含まれているため、ファイル サイズは、カメラからの通常の RAW ファイルよりも 3 倍大きくなります。この Fujifilm ファイルには、Fujifilm HDR RAF という正式な名前があります。
通常のRAW現像ソフトは、1枚目のRAWデータのみを処理し、2,3枚目は無視します。
3枚の画像データを使うには、DNGに変換する必要があります。
簡単にいえば、Fujifilm HDR RAFは、ブラケット撮影された3枚の画像を1つのファイルに入れるコンテナにすぎません。
Understanding Fujifilm High Dynamic Range 2021/02/15 Chris Lee
https://petapixel.com/2021/02/15/understanding-fujifilm-high-dynamic-range/
1-3)まとめ
HDR撮影モードがあるカメラで、HDR画像のRAWファイルを作成することは、ブラケット撮影された複数の画像をカメラ内で、撮影後すぐにDNG変換することを意味します。
2022年9月現在で、この機能のあるカメラはなさそうです。
フルサイズセンサーのカメラを販売しているカメラメーカーにとっては、カメラ内で、HDR画像のDNG(RAW)ファイルが出来てしまうと、フルサイズセンサーのカメラが売れなくなるので、メリットは少ないです。
ということは、オリンパスと富士フイルムに期待するしかありません。
2)AEブラケティング
HDR撮影機能は使えないので、AEブラケットで撮影された3枚の画像を合成することがHDR画像作成の基本になります。
AEブラケティングは次の様に説明されます。
AEブラケティングは一度シャッターボタンを押すと、露出を「適正」「オーバー(明るい)」「アンダー(暗い)」の順に変えながら3コマ連写で記録します。
この説明は、間違っていませんが、分かりにくいです。
露光を変える要因は、シャッター速度、絞り、ISO感度です。
絞りを変えると被写界深度が変化するので、重ね合わせができない写真になります。
そこで、シャッター速度かISO感度を変えることになります。
フィルム時代であれば、フィルムを入れ替えたブラケット撮影はできないので、自動的に、シャッター速度を変えることになります。
なので、伝統的に、AEブラケティングとは、シャッター速度を変えたブラケット撮影の意味で使われてきました。筆者は、、シャッター速度ブラケット撮影と言うべきだと思いますが、用語はレガシーを引いています。
AEブラケティングで、ISOを変える場合は、AEブラケティングとは呼ばずに、ISOブラケティングと呼ばれています。
3)課題と作例
AEブラケティングでは、撮影枚数(3,5,7)と撮影刻み(2EV、1EV、1/2EV 1/3EV)が設定できます。枚数と刻みの種類はカメラによって違います。
撮影時の課題は、この設定と、手ブレ対策です。
写真1は、パナソニックのコンデジのLX100で撮影しています。
この機種、一応、光学式手ブレ補正機構内蔵と書いてありますが、現在のII型に比べて、「初代の手ぶれ補正はほとんどないようなものだったの」と言っている人もいます。
写真1の左は、AEブラケティングで撮影した4枚の画像をdarktableでHDR合成しています。右は、普通の画像です。
左は、手ブレによって、ずれた画像が合成されています。
この場合には、三脚を立てる必要があります。
写真2は、オリンパスのEM1 mkIIで、撮影しています。
左のHDR画像は、HDR1モードのカメラ内合成の画像です。
右の通常の画像と比べて、差がわかりません。
つまり、この場合であれば、三脚を立てなくとも、AEブラケティングに成功したことになります。
AEブラケティングの中身を見てみます。
写真1の撮影条件は以下でした。露光の刻みは1EVです。
シャッター速度、絞り、ISO
1枚目 1/10000 F8 ISO400
2枚目 1/5000 F8 ISO400
3枚目 1/2500 F8 ISO400
4枚目 1/1250 F8 ISO400
これをみると、1枚目と2枚目は、1/4000秒を超えているので、電子シャッターが使われています。1EVでは、シャッター速度が2倍に変化するので、3EVでは、シャッター速度が8倍変化します。
写真3は、オリンパスのEM1 mkIIで、露光の刻みは2EVで撮影した画像を、darktableでHDR画像合成しています。
もとの画像は、次の撮影条件です。
シャッター速度、絞り、ISO
1枚目 1/1600 F8 ISO200
2枚目 1/400 F8 ISO200
3枚目 1/100 F8 ISO200
4枚目 1/25 F8 ISO200
5枚目 1/6 F8 ISO200
シャッター速度の最速は、1/1600秒なので、電子シャッターは使われていませんが、最長は、1/6秒です。
EM1 mkIIは、2秒くらいまで、手ブレしないので、写真3では、画像のずれがありませんが、EV刻みを大きくして、枚数を増やすと、条件が厳しくなります。
三脚が必要か、手持ちで可能かは、シャッターチャンスを大きく左右するので、事前に手持ちのカメラの性能をテストしておくべきです。
今回テストするまで、ブラケット撮影は、三脚必須という思い込みがありましたが、手持ちで可能な場合もあることがわかりました。手持ちブラケット撮影が可能であれば、HDR画像編集は、手軽にできます。
4)要望
HDR撮影が、複数枚数を画像を合成して、そのカメラで撮影できる最大のダイナミックレンジの画像データを作成するのであれば、シャッター速度とISOを同時に変化させるブラケット撮影があるべきですが、今のところその機能のあるカメラはありません。